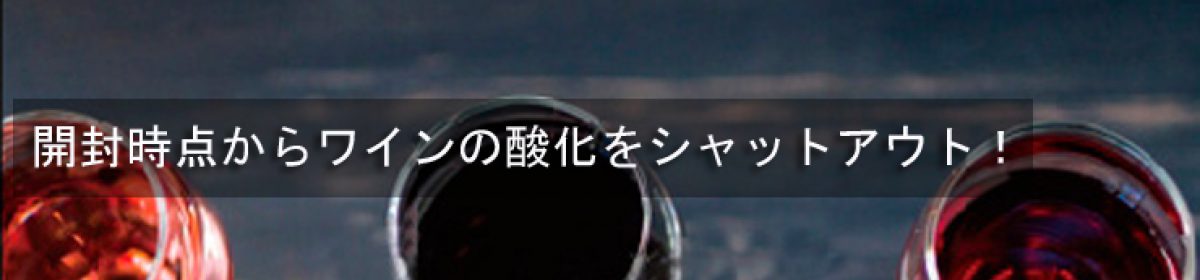①柔らかくグラスを持つ
グラスを持つ手はソフトに。グラスの長い足の部分を軽やかに持つだけで、扱い慣れていると分かります。グラスの淵を持つ人は相当使い慣れている感があります。
②飲む前に香りを確認する
飲む前に必ず香りを確認しましょう。ワインは香りと一緒に楽しむ飲み物です。香りを確認する仕草をするだけでワインの楽しみ方を知っていると見て取れます。
③軽くグラスを回す
ワインの香りは空気と接触することでドンドン変化します。グラスを軽く回して、中の液体を空気と馴染ませてあげましょう。この所作が加わると「ワインを嗜んでいる」ことがハッキリわかります。
④目をつむって飲む
ワインは香りと一緒に飲み込みます。その際、目をつむって飲みましょう。途端にエレガントな印象になります。
⑤ゆっくり飲む
スパークリングワインを含め、ワインは喉を潤すように飲んではいけません。ワインはグラスに注いでから時間の経過と変化も楽しめます。ゆっくり、一口づつ、香りと味を確認しながら、その変化を楽しみましょう。