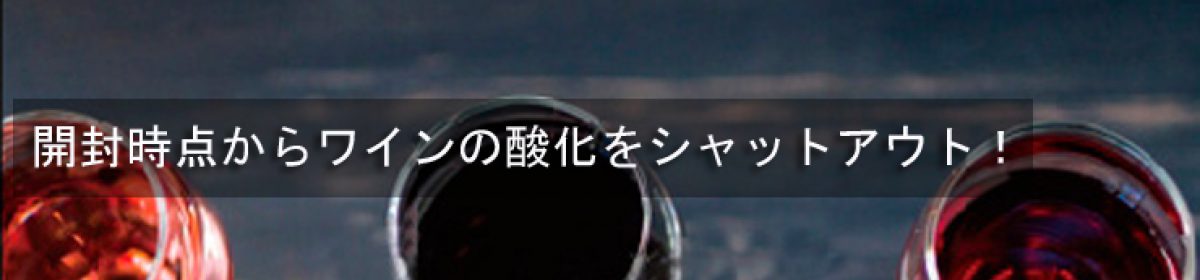アロマ(aroma)とは、ぶどう本来の香りと発酵段階で生まれる香りのこと。
アロマ(aroma)とは、ぶどう本来の香りと発酵段階で生まれる香りのこと。
アロマは、第1アロマ、第2アロマ、第3アロマの3つに分けられる。第1アロマはぶどう本来の香り、第2アロマは発酵過程で生成された香り、第3アロマは熟成期に生成された香り。このうち、第1と第2アロマが「アロマ」、第3アロマが「ブーケ」と称される。
アロマとブーケはよく混同されるが、アロマはワインをつくる過程で生まれる香りで、ブーケは若いワインを樽の中で熟成させる間に生まれる香りとなる。
毎年11月の第3木曜日に解禁されるボジョレー・ヌーヴォーは、熟成させない若飲みタイプなのでブーケをほとんど感じられない。
アロマを楽しむには、ワインをグラスに注いだときに立ちのぼる香りを味わう。一方、ブーケを楽しむには、グラスに注いだワインを大きく揺らし、空気に多く触れることで立ちのぼってくる香りを味わうのが良い。