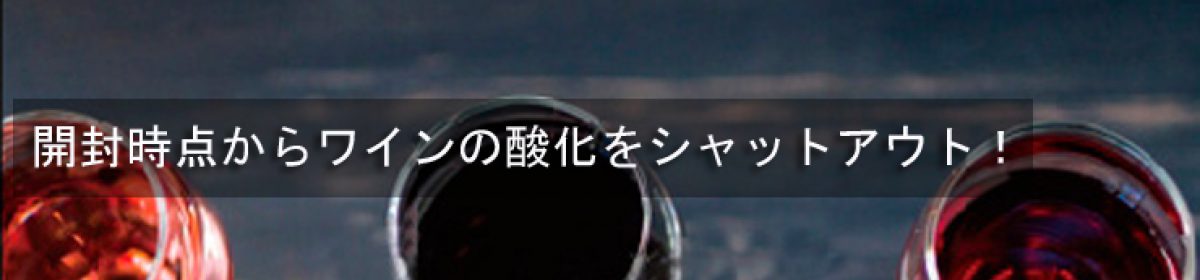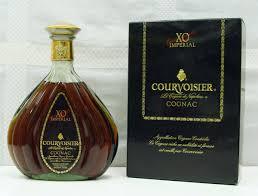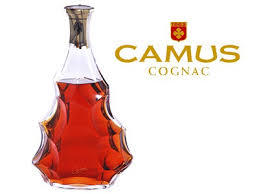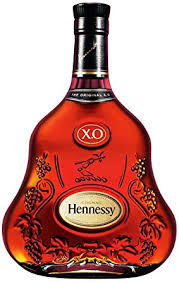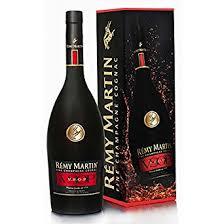「ヴィンテージ」とは、そのワインの原料のブドウが収穫された年度をいいます。
ただ、「ヴィンテージワイン」となれば、年代物とか年代物の高級物、の意味でも使われます。
なぜぶどうの収穫年によってワインの値段が変わるのかということについてですが、その根本は、年によって収穫されるぶどうの状態が変わるので、それにしたがってワインの味や風味も変わる、というところにあります。
ワインとは、ぶどうだけ、すなわち果物で造られる飲み物です。
その原料のぶどうが作られた年の天候の善し悪しがぶどうの生育に影響し、ワインの品質を決めることになります。
たとえ同じ畑から獲れたぶどうであっても、去年と今年とでは気候条件、気象条件、病害虫の発生条件などが随分異なるということはよくあることです。
ですから、結実したぶどうが去年と今年とでは異なるというのが自然です。
とすると、その原料ぶどうから造られるワインも全く同じにはならないというのが自然です。
このことから、ヴィンテージによってワインの風味や味が全く別物のように異なるということはないにせよ、違いが生まれるというのは納得のいく話です。
ヴィンテージの特徴を知ることがワインの飲み頃の目安ともなります。
ワインは古いだけで価値があるのではなく、いつ頃美味しさのピークを迎えるかを知る楽しみもあります。