
ソムリエなど、プロが使うタイプです。てこの原理でコルクを持ち上げるもので、なれると一番あけやすいのですが、やはりそれなりに力は必要です。
-ワイン・日本酒の酸化防止ワインセーバー-

ソムリエなど、プロが使うタイプです。てこの原理でコルクを持ち上げるもので、なれると一番あけやすいのですが、やはりそれなりに力は必要です。

芸術的な握りの部分をもつものを除き、価格的には一番手ごろなタイプですが、力が要ります。瓶を股に挟んで、力いっぱいエイヤ!、何てこともあり難しいですね。

お酒の中でもフルーティーな感じの強いワインですが、ワインのアルコール度数はどれほどでしょうか?
度数は産地やぶどうの品種によってかなり幅があります。
ワインの基本的なポイントですが、ぶどうに含まれる糖度がアルコールに変化することでお酒になります。
従って、ぶどうの糖度が高いとアルコールの度数が高めのワインになるということです。逆に糖度が低ければアルコール度数も低めになるということです。
ただ実際には工程の違いもあるので必ずしも同じようなアルコール度数になるわけではありません。甘めのワインであれば度数が7%ほどのこともあります。一方アルコール度数が14%を超えるものもあります。またぶどうの品種によって常に糖度は一定になるわけではありません。
日射量が多ければ糖度があがりやすくなりますし、涼しければ下がるでしょう。このようにアルコール度数を左右する要素はいろいろあります。
大雑把に言えば辛口のワインであれば度数は10.5~14.5%くらいです。甘めのワインだともっと低く6~12%ほどです。

ワインには通常の赤ワインと白ワインの他、スパークリングワインとかフルーツワインなどいろいろな種類があります。
やはりそれらの中でも圧倒的に有名なのは赤ワインと白ワインです。
どちらも上質なワインの産地であるフランスで作られるものですが、両者の最大の違いは色でしょう。ではなぜ赤ワインは赤く、白ワインは白くなるのでしょうか?
ワインの色については実は少し細かな話があります。しかし基本的なことを言うと、まず製造方法が違うからという点が挙げられます。赤ワインを作る時には主に黒ブドウ品種が使用されます。そして白ワインの場合は表面が緑っぽい品種のブドウが使われます。
ワインを作る時、赤ワインの場合は皮や種を使用します。皮は黒っぽいですから、皮を混ぜ込むことで色素が出てきます。これが赤ワインの色のもととなります。白ワインの場合は基本皮や種は使いません。果肉のみを使います。ですから赤くなったりしないのです。
また白ワインに使われるぶどう品種の皮ももともと赤いものではありません。まとめると赤ワインの色は皮の色というわけです。
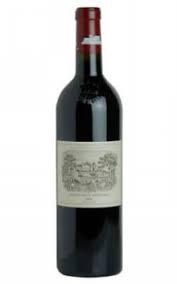
ワイン1本750mlあたりに使われるぶどうの量はどれくらいでしょうか?ワインにはたくさんの種類があるので一概には言えませんが、おおよそ1.2キロ~1.5キロの量のぶどうが使用されます。ぶどうの量の半分を少し下回るほどが最終的にワインとなるわけです。
ただこれはテーブルワインの場合です。高級ワインともなれば質が第一ですので、その量はかなり変わってくるかもしれません。

ワインコーナーを見ていると、瓶の形にはいろいろな種類があるものの、容量は750mlのものが多いことに気づきます。
これはビールのカンなどにも言える事ですが、なぜワインの瓶の容量は750mlのものが一般的なんでしょうか?
簡単にいうと「分かりやすかったから」です。といっても日本人にとって分かりやすいからではなく、ヨーロッパの国にとってです。もう少し具体的に言うとイギリスにワインを輸出する時に分かりやすかったからです。イギリスはワインの生産では有名ではないものの、ワインを日本よりも多く消費する国です。

ワイン消費大国であるフランスとイタリアの1人当たりの消費量は、なんと年間約60リットル。ワイングラス1杯で100mlを飲むとしたら、600杯分。
ちなみに日本は年間2~3リットル。

中世ドイツの騎士達は履いている長靴にビールを注いで飲んでいた。
後に木・竹・陶器・象牙・銀などで今のようなジョッキが作られるようになった。

アルコールには熱量があり、その熱量に応じて体が熱くなり顔も赤くなる。
もうひとつの理由は、アルコールを分解する酵素が弱いため、分解されずに残るアセトアルデヒドという物質が頭部に血管拡充を起こし、顔が赤くなる。
ちなみに、アルコールは20%が胃で吸収され、80%が腸から吸収される。

グラスをぶつけた勢いで互いの酒が相手のグラスの中にとび、毒を盛られていないことを確認するために行われたのが起源。
他にも、音を立てることでお酒に宿っている悪魔を追い払うため、毒が入ってないことを証明するために家の主と客が同時に飲み干す合図に使ったとも言われている。