 ボトルを寝かせる事により、常にコルクが湿っている状態となるので、酸化の心配がなくなります。(中には上下を逆さまにして保存する方もいるようですが、澱(おり)が
ボトルを寝かせる事により、常にコルクが湿っている状態となるので、酸化の心配がなくなります。(中には上下を逆さまにして保存する方もいるようですが、澱(おり)が
口の付近にたまってしまうので、グラスにそそぐ時に大変なことになりそうです。)
例外はスパークリング・ワイン。スパークリング・ワインは立たせて保存してください。
炭酸ガスにより、コルクに充分な湿気が供給されるので、逆に立たせて保存したほうが
美味しいようです
-ワイン・日本酒の酸化防止ワインセーバー-
 ボトルを寝かせる事により、常にコルクが湿っている状態となるので、酸化の心配がなくなります。(中には上下を逆さまにして保存する方もいるようですが、澱(おり)が
ボトルを寝かせる事により、常にコルクが湿っている状態となるので、酸化の心配がなくなります。(中には上下を逆さまにして保存する方もいるようですが、澱(おり)が
口の付近にたまってしまうので、グラスにそそぐ時に大変なことになりそうです。)
例外はスパークリング・ワイン。スパークリング・ワインは立たせて保存してください。
炭酸ガスにより、コルクに充分な湿気が供給されるので、逆に立たせて保存したほうが
美味しいようです

冷蔵庫の中は乾燥している為、コルクも乾燥し、結果、ワインが酸化してしまいます。
また、湿度の多すぎは、カビのもと。ラベルに付いたカビはワインの質には影響ありませんが、
将来そのワインを売ろうと思っている場合、商品価値が下がってしまいます。
適切な湿度は60~70%です。

ワインの中のタンニンは、成熟すると共に縦長に繋がり、まろやかな味になります。
しかし振動を与えると、このワイン成分の構成に変化が生じてしてしまいます。
ワインを貯蔵する時は、くれぐれも洗濯機の横には置かないようにしましょう♪

たとえ緑色のボトルに入っていても、やはり光の影響で、ワインの質は変わってしまいます。
ワインセラーは光に当たらない、家の奥に置いて下さい♪
また、お店で買う時、窓辺に陳列してあるワインには絶対に手を出さないようにご注意!

涼しい温度が適切って、じゃあ何度に保てばいいんじゃい?と思われますよね。
日本では、大抵摂氏18度ぐらいが適温といわれていますが、これは、ワインを
どれくらいの期間貯蔵したいのかによって微妙に変わってきます。
UCデイビスの調べによると、摂氏40度(華氏104度)では、2週間以内にワインが
だめになってしまいました。
摂氏30度(華氏86度)では、1ヵ月経った時点で、ワインがだめになるということはありません
でしたが、ボトルの中での成熟はとても早かったという事です。(すぐ飲んじゃいましょう♪)
逆に、温度をぐっと下げて摂氏7度(華氏45度)にした場合、少なくともボトルの中での成熟は
進まなかったようです。(永遠に貯蔵できるか否かは、残念ながら不明です)
摂氏21度(華氏70度)では、ワインを損ねることなく、最高の飲み頃まで何年か貯蔵できます。

温度が上がったり下がったりすると、コルクが収縮・膨張して、結果ボトルの中に空気が入り込み
お肌にも大敵の「酸化」が進んでしまいます。また、華氏80度(摂氏27度)以上の温度の中では、たとえ短期間でもワインの質は変化してしまいます。
ですから、ワインの貯蔵に大切なのは、温度を一定に保つ事。それも涼しい温度が適切です

フランスには「アペロ」という習慣があるのをご存知ですか?
夕方過ぎになると、よく仕事帰りのパリジャンたちが、ワインボトルを持って歩いている姿を見かけることがあります。彼らは、友人や恋人たちと「アペロ」の待ち合わせに向かっているのです。
アペロとは「Apéritif(アペリティフ)」という言葉の略で、日本語では「食前の一杯」といったところ。夕食前にお酒を一杯飲みながら、オリーブやスナックなどのおつまみを食べ、気心知れた仲間同士で楽しくおしゃべりをするのです。
集まる場所は、お店や自宅など様々ですが、だんだんと暖かい季節になってくると、夜遅くまで照る太陽の光を浴びながら、セーヌ川の川辺でアペロを楽しむ人が増えてきます。
みなワインを楽しむ傍らで、ある若者はギターを弾き、カップルは人目をはばからずキスに夢中になり、ご老人はただパリの景色を眺め、思い思いの夕方を過ごしています。
アペロは、フランス人の生活に欠かせない、ワインの楽しみ方の定番のひとつなのです。
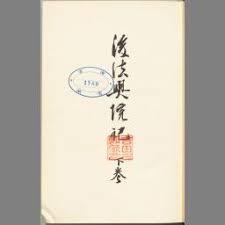
日本の文献によると、日本でワインが初めて登場しているのは室町時代です。
その当時の文書である「後法興院記」によると、「珍蛇(チンタ)」というお酒を飲んだという記録があります。
この、珍蛇はスペインやポルトガルから伝わったワインのことであると考えることができ、この頃からワインが嗜まれていたと考えることができるのです。
世間一般的に流通をしていくとされているのは、1549年にイエズス会の宣教師であるフランシスコ・ザビエルがキリスト教布教のために鹿児島を訪れた際、布教した地域の大名にワインを献上したことであると言われています。
そのあと、ペリーが来航したときにも日本にワインを献上したとされており、そこからワインが世間へと浸透していくのです。

一般的にワインのボトルというのは1本あたりに750ミリリトトル入っています。
これは、フランスで有名なボルドーやブルゴーニュのようなワインも特徴あるボトルの長細いアルザスでも750ミリリットルです。
しかし、日本のワインの中には720mlという容量のワインがあります。
このワインの量が半端なのには、日本のワイン作りの歴史と関係があります。
日本でアルコールを計測する単位は1合が180ミリリットルであり、日本酒の4合である720ミリリットルで一升瓶を作っていました。
この一升瓶にワインを入れて製造していたので日本には720ミリリットルという半端な容量のワインがあるのです。
これは、日本で製造されているワインならではの特徴です。
そのため、国産ワインを購入するときには720ミリリットルのものを見つけると古くから製造がされているワインの目印になります。

ワインには、ブドウに含まれている栄養成分のほぼ全てをワインの中に取り込んでいますから、多くのミネラル・ビタミン・ポリフェノールなどが含まれています。
これらの栄養素は、通常、食品で摂取する場合には食品に含まれている量の30~40%しか吸収されませんが、ワインで摂取する場合はこれらの栄養素の100%が体に吸収されると言われています。
このことから、ワインには抗酸化作用・血圧降下・抗ガン作用・殺菌作用など多くの効果が期待されるのです。
たとえば、動脈硬化やガンの予防になるといわれている赤ワインに多量に含まれているポリフェノールの効果は、ポリフェノール含有量の多い野菜に比較して20倍以上もあります。
また、ワインに多く含まれているカリウムは、体内のナトリウムと結合することで塩分を減少させることから、高血圧予防に役立ちます。
グラス約1杯飲むだけで、通常の血圧に対して10 mmHg程度低下させます。
ワインを飲んでも血圧は上がることはなく、むしろ下がっていきます。
特にビンテージものなど長期貯蔵ワインの場合は分子の高分子化が進み、高級アミノ酸が発生しています(高級アミノ酸は糖尿病予防に効果があると言われています)。
この高級アミノ酸はポリフェノールと同じ働きと効果があると言われますから、高級ワインを少しずつ飲むのが理想的な飲み方と言えるでしょう。