
ワインと一緒に摂取するといいものとして一般的に言われるのは、「チーズ」です。
チーズのメチオニンという成分が、アルコールの摂取で疲れた肝臓の働きを助けてくれる効果を期待できるのです。
小魚に含まれるカルシウムはその30%程度、野菜などに含まれるカルシウムは17%程度しか吸収できません。
しかし、チーズに含まれるカルシウムは、50~60%が体内に吸収されます。
ワインなどの摂取による血液アルコールを中和する働きがあるのはカルシウムであり、チーズにはこのカルシウムが多量に含まれているのです。
チーズ以外でワインと一緒に摂取するといいと言われるのは、ビタミンB1・タンパク質・抗酸化成分を含んだ食品です。
ビタミンB1を含む食品には、アルコールの代謝を高め・促進する作用があります。
具体的には豚肉、小麦胚芽、大豆、ひまわりの種、乾海苔などです。
たんぱく質を含む食品は、肝臓を守る働きがありますからワインと一緒に摂取するとアルコールの害を予防できます。
具体的には不飽和脂肪酸が豊富な魚、卵、牛乳や乳製品などです。
抗酸化成分を含む食品をワインと一緒に摂取すると、ポリフェノールの効果がより高められます。
抗酸化成分の水溶性のものにはビタミンCがあり、野菜や果物に多く含まれています。
また、抗酸化成分の脂溶性のものには、ビタミンEとカロチンがあります。
ビタミンEは植物油、穀類、豆類、動物性食品などに含まれていますし、カロチンは緑黄色野菜に多く含まれています。
こうした食品をワインと一緒に上手に摂取して、ワインを健康的に楽しんでください。
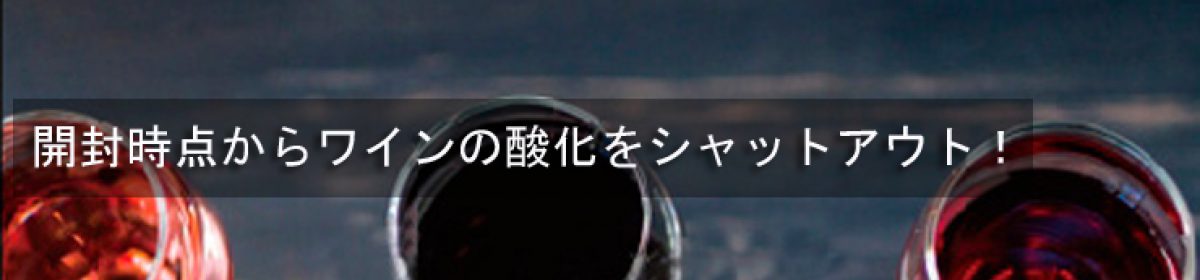


 主原料が牛肉と豚肉のドライソーセージで、発祥はイタリアです。
主原料が牛肉と豚肉のドライソーセージで、発祥はイタリアです。




