
元はフランス語で 区画・領域・領地を示す言葉である
一般的には自社で畑を所有して
栽培・醸造・瓶詰めを一貫して行うワインの生産者を指します。
IMG_0633
同義語で使われることが多いものとしては シャトー という言葉が挙げられる。
かつてブルゴーニュではドメーヌが最も重要といわれている時期もありました。
その理由としては
ドメーヌは小規模で行っている生産者が多く、ブドウの管理も細分化しているため
その結果、品質がとても良いといわれるからです。
デメリットとしては
その年の出来が悪い場合では
品質を保つ為に不出来なブドウをネゴシアンに売り渡し品質のいいものを残しそこから出来上がるワインが少量である為に価格の高騰がデメリットとしてあげられます。
一方
ネゴシアンは、生産者からブドウを買い付けを行い
様々なワインを取り扱うことが出来ます。
そして価格が安く販売することが出来るメリットがありますが
大量に仕入れることは個性少なさと品質の低下に繋がるとの問題もあります。
しかし、現在では
現在ではネゴシアンも自社で畑を所有しながら
有能な生産者からワインを買い取り自社で熟成を行うなどの様々な形態での販売をするなどしています。
一概に「ドメーヌもの」と「ネゴシアンもの」の良さの線引きはとても難しいものともなっています。
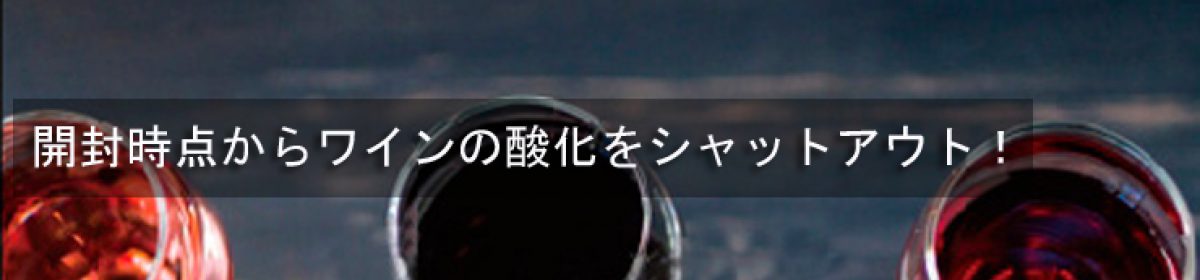




 シャンパーニュの瓶は、上部がホイルの様なもので巻かれています。一本一本瓶の中で発酵させるシャンパーニュ。醸造する中で滓(おり)を泡の力を使い噴射させ、取り除く行程があります。その際、どうしても一本一本の量に差が出てしまうのです。それを隠しているのがあのホイル。ただの飾りのようにも思えますが、ちゃんとした役割があるのです。
シャンパーニュの瓶は、上部がホイルの様なもので巻かれています。一本一本瓶の中で発酵させるシャンパーニュ。醸造する中で滓(おり)を泡の力を使い噴射させ、取り除く行程があります。その際、どうしても一本一本の量に差が出てしまうのです。それを隠しているのがあのホイル。ただの飾りのようにも思えますが、ちゃんとした役割があるのです。


