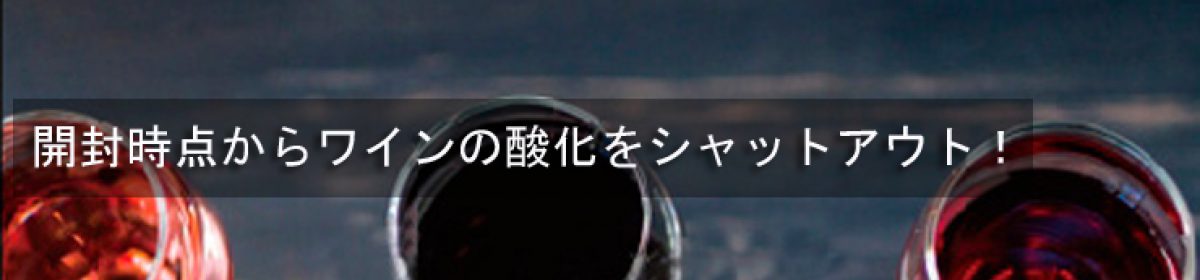①味わいで合わせる
最も基本のマリアージュのルールです。あっさりとした味付けのものにはあっさりしたワインを、コクのある味付けのもにはコクのあるワインを合わせます。
魚に白ワイン、肉に赤ワインのように食材で合わせたくもなりますが、それ以上に重要なのは調味料やソースです。例えば、レモンを絞って食べるような鶏の唐揚げは白ワインとも合います。魚の煮付けなどは、醤油やみりんが効いているため、赤ワインとも合うのです。
②産地で合わせる
ワインは郷土色が強い飲み物でもあります。もともと食文化と密接に関わっているので、郷土の料理には郷土の料理が合います。
例えば、アルザス地方のシュークルートにはアルザスの白ワイン。牛肉の赤ワイン煮込みには、ブルゴーニュの赤ワイン。ブイヤベースにはプロヴァンスのロゼワインなどです。
③品格で合わせる
ワインと料理のバランスは非常に重要です。例えば、キャビアやフォアグラ、オマールエビなどの高級食材には高級なワインを組み合わせます。簡単なおつまみで飲む程度なら、カジュアルなワインの方がバランスが良いです。
マリアージュはお互いの良さを相乗効果で引き出すもの。どちらか一方が突出していると、反対にお互いの欠点が見えてしまいます。