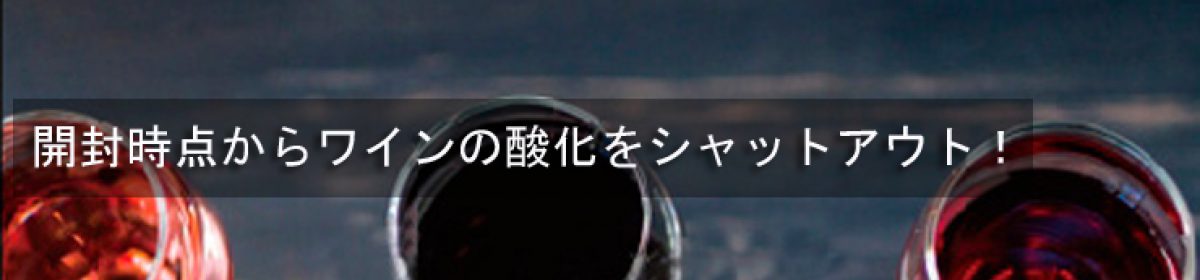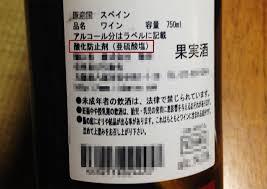シャンパンとは、フランスのシャンパーニュ地方でつくられるスパークリングワインだけが名乗ることのできる、いわば産地名に由来した名称です。しかも、シャンパーニュ地方でつくられればすべてがシャンパンと呼べるわけではなく、フランスワインの法律であるAOC(原産地呼称統制)に従って栽培から醸造、そして瓶内2次発酵まですべてが厳密に行われ、最終的に品質検査を受けて合格したものだけが「シャンパン」と名乗ることができるのです。かつては、ワインのカテゴリー名であるスパークリングワイン全般のことを「シャンパン」と乱用して呼んだ時代もありましたが、現在では他の産地のスパークリングワインを「シャンパン」と名乗ることは国際的に禁止されています。