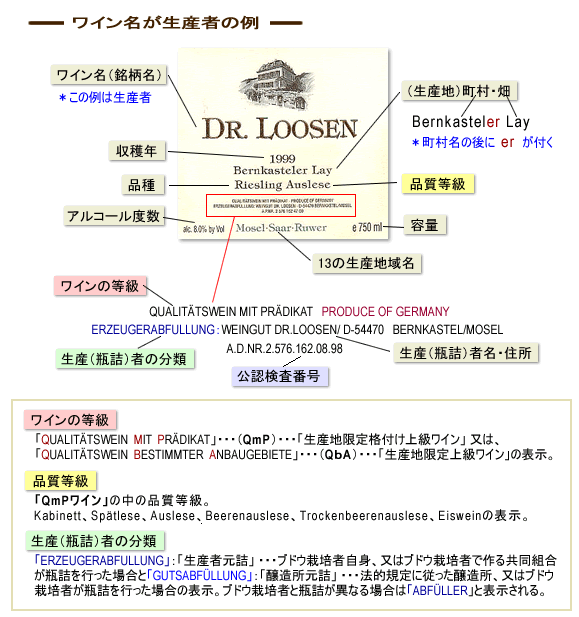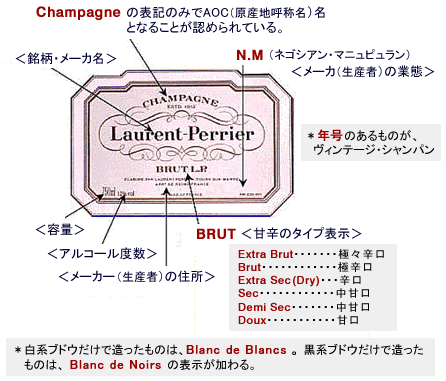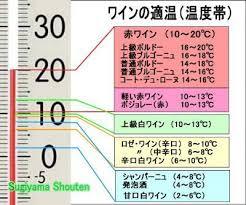
-ワイン・日本酒の酸化防止ワインセーバー-
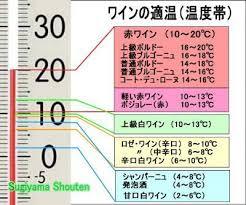

ワイングラスについた口紅は、指でぬぐって、その指をそっとナプキンでぬぐいましょう。でも、パリッと糊の効いた真っ白なナプキンに真っ赤なルージュやグロスがべったり、はちょっと考えもの。食事の席に着く前に、ティッシュで抑えておく気遣いも、大人のマナーのうちのひとつです。

会食中に、これ以上ワインを注いでもらわなくて大丈夫、と思う時は、ワインを注がれそうになった時に、ワイングラスの上に手をかざすようにしましょう。これが、「もういりません」のサイン。もっと飲みたい人がいる席で、「いりません」と声に出して空気を気まずくすることのない、スマートなやり方です♪

ワインの栓がコルクである理由は、柔軟性、弾力性があり、気体や液体を通さず、腐敗に対する抵抗力も強いという性質が、ワインの栓に最適だからです。ワインは酸素と触れると劣化しやすく、逆に空気を断って長く熟成させると香味が向上することが多いという特徴を持っています。この特徴を生かすために、17世紀末頃からコルク栓が使われるようになりました。

澱(オリ)が舞い上がりにくくするためです。赤ワインは長く熟成させていると、タンニンや色素の成分がワインに溶けきれなくなり、澱(オリ)としてワイン中に沈殿してくることがあります。
オリの出るワインばかりではないのですが、こうした昔ながらの工夫がボトルデザインの伝統としても残っているというわけです。

ワインをレストランなどで頼んだ場合、多くの場合はホストテイスティングが求められます。ソムリエなど、給仕係から注文したワインがグラスに注がれた時、間違ったホストテイスティングをすると、少し恥ずかしい思いをしてしまうかもしれません。
まず、ホストテイスティングの目的は、注文通りのワインを持ってきてもらえたか、コルク由来のカビ臭(ブショネ)などの異臭が無いか、などを確認する作業です。まず、ラベルを確認、先にコルクが抜かれていないかを確認、グラスに注がれたから香りを嗅ぎ、違和感が無ければ「大丈夫です」と伝えるだけです。
僕の好みではないとか、思ったより色合いが濃いから変えてほしいなど、ワイン自体に問題が無いのに交換はできません。さらに、グワングワングラスを回し、香りをチェックして、「オレンジピール、ミッドパレッドにナッツ」など、香りを表現する場でもありません。あくまで、事実と品質の確認がホストテイスティングの目的です。

一般的な日常のワインであれば、開栓後でもコルクなどで再度ふたをして冷蔵庫で保存しておけば1週間程度はそれなりに飲めるでしょう。
しかしそれ以上となるとワインが酸化して変色してくるのが目に見えて分かるようになります。これはロゼや白ワインだとより顕著となるでしょう。その場合はお世辞にも美味しく飲めるとは言えません。
体に害がある状態になるというわけではありませんが、基本的にはそのワインを楽しむというよりも料理酒として使うことをおすすめします。
赤ワイン(フルボディ) ⇒ 約1週間
赤ワイン(ライトボディ) ⇒ 5日程度
白ワイン(辛口) ⇒ 約1週間
白ワイン(甘口) ⇒ 2週間~4週間程度

一般のワインに賞味期限が記載されていない理由、それを一言でいえば、ボトル内でも熟成が進んでいるからと言えるでしょう。これは言いかえれば飲みごろとなる時期に幅がありすぎるため、賞味期限という概念での表示が難しいということでもあります。
これにはワインのある特徴が関係しています。ワインというのは一般的な食品と違い、製造された直後からすぐに劣化が始まるわけではないという点です。
ワインボトルに瓶詰めされた後も熟成を続け、その時々によって香りや味わいを変化させ、それを楽しむ飲み物でもあります。瓶詰め直後が必ずしも飲みごろであると言えないということです。中には何十年という熟成期間を経るものもあります。
ワインボトルに記載があるのは収穫年です。この年からどれくらいの熟成期間を経たものが自分の好みになるかを考えながら楽しむのがワインの大きな魅力の一つでもありません。
このようにワインは通常の保存環境で3年のシェルライフがあり日本だけに限らず諸外国においても賞味期限の記載はありません。これらがワインに賞味期限が記載されていない理由と言えるでしょう。