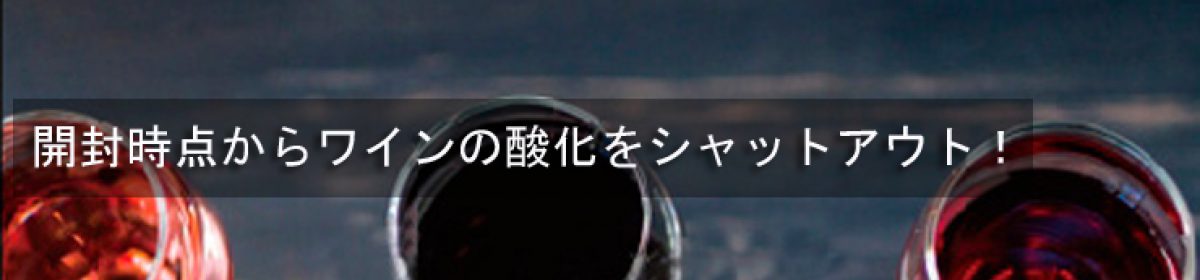ワイン初心者だと、ワインをボトルからデキャンタに移して空気に当てるデキャンタージュは、聞いたことはあっても、あまり馴染みがないかもしれません。でも、わざわざデキャンタージュする必要が本当にあるのでしょうか。将来ワイン通になりたいなら、これは知っておいたほうがいいことです。
そもそもデキャンタージュとはなんでしょうか。私の友人で、蒸留酒認定スペシャリストの資格を持ち、ソムリエ研修中のTia Eshouさんに聞いてみました。彼女は大手の酒類流通業者で勤務しています。デキャンタージュは、ワインからかすを取り除き、ワインを酸化させます。別の言い方をするなら、ワインに呼吸させるために行なうとEshouさんは説明しています。
これをすると、ワインが「ぱーっと花開く」のです。ワインの中に空気を入れると、酸化と蒸発がはじまって、味も香りも際立ちます。また、これによりワインの酸味と亜硫酸塩臭も飛んで、滑らかな味わいになることが多いのです。
なるほど。でも、どんなワインでもボトルやボックスを開けたときデキャンタージュをしなければならないのでしょうか。そういうわけではないとEshouさんは言います。
初心者の場合は、いつもより値段が高いワインを開けるとき(少なくとも1本50ドル以上のワインのときです)、ちょっと古めの赤ワイン、タンニンが多いワインのときだけでいいでしょう。白ワインやスーパーで売っている2〜3年前にできたワインなら必要ありません。お求めやすいワインはたいてい、デキャンタージュしないでそのまま飲んでもいいようにできているので、コルクを抜いたらすぐに飲んでも大丈夫だとEshouさんは説明しています。
とは言え、ワインは値段に関係なく、ちょっと空気に当てるのはいいことです(特に激安であまりおいしくないワインの場合はおすすめします)。でも、だからと言って、わざわざ立派なデキャンタを買う必要はないとEshouさんは言います。グラスに注いだワインを飲む前にちょっとゆらゆら揺らして空気に当てるだけでもいいのです。Eshouさんによれば、安物のワインを美味しく飲むには、適切な温度で飲むほうがもっと重要なのだそうです。白ワインなら55℉ぐらい(約12.8℃)に冷やして、赤ワインなら、冷たいと感じない程度の温度で室温より少し低い65℉前後(18℃前後)で飲むのがおすすめです。
「安物のワインをデキャンタージュしたらどうなるの?」と私が冗談めかして聞くと、「やって損はない」とEshouさんは笑って言いました。デキャンタージュする前とは別の味わいを楽しめるかもしれないので、やってみる価値はあるそうです。それなら、毎回デキャンタージュしてみる価値はありますよね。わざわざデキャンタージュしないときは、グラスの中でワインを2〜3回ぐるぐる回転させるだけでも効果が期待できます。
Image: Flickr(1, 2)
Patrick Allan – Lifehacker US[原文]