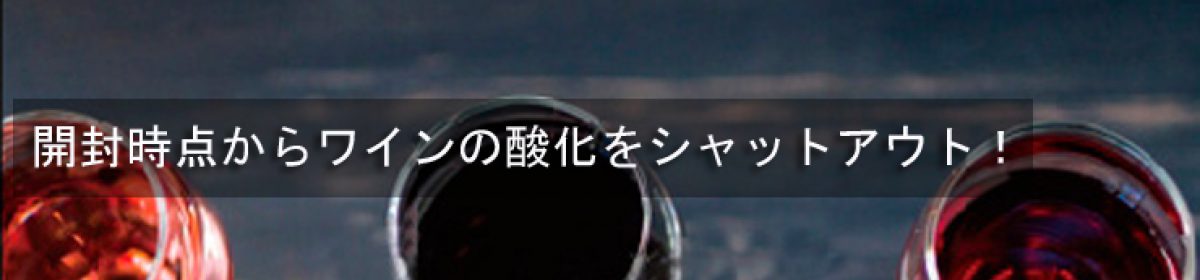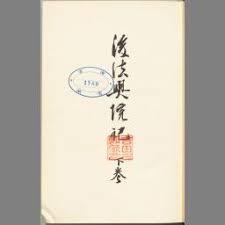「カチ割り」とは、いわゆる「ロック」。大きめのグラスにロックの氷を入れ、冷やしていない手ごろな価格の赤ワインを注ぎます。 ぶどうの品種はメルロかカベルネ・ソーヴィニヨンがいいでしょう。
ワインの赤色と氷が輝き、素敵なグラデーションがとてもきれいです。
赤ワインの果実感をスッキリとした口当たりで楽しめますので、お好み焼や焼き鳥など気楽な食事によく合いますし、夏の暑い日などには最高です。
「そんな飲み方は邪道!」と思われる方もおありでしょうが、意外にとてもおいしいので、一度試してみてください。
ドイツに行った時、現地の人に聞いた話なのですが、実はこの飲み方のルーツは、ナポレオンらしいのです。
ナポレオン ナポレオンは「シャンベルタン」というブルゴーニュの特級畑のワインがお気に入りで、進軍のときはいつも「シャンベルタン」を用意していました。
あまりお酒が強くなかったナポレオンは行く先々でワインを水で割って飲んでいたと言われています。
ドイツのフランケン地方に進軍した時、若い女性がワインの入ったグラスをナポレオンに差し出しました。
ナポレオンはそのワインを泉の水で割って飲み「Toujour sl’amourトゥジュール・ラムール(愛よ永遠に)」と言いました。
ワインを渡してくれた女性が美しかったら言ったのか実際の所は解りませんが、フランケンの人々はフランス語が理解できなかったため、独語的に「リスーレ・ムーレ」と聞こえ、女性のことではなくワインを水で割った飲み物のことを「リスーレ・ムーレ」と呼ぶのだと思ったようです。
この言葉が徐々に「ショーレ・モーレ」に変化していき、今でもドイツでは昼食の時などワインを水やソーダで割って飲むことを「ショーレ」と呼んでいます。
この話を聞いて、30年ほど前に、「焼鳥屋」を始めるという友人からお店で提供する飲み物の相談を受けた時、お客様に気軽にワインを飲んでもらおうと水の代わりに氷を入れる「カチ割りワイン」を考案しました。
邪道などと言わず、気軽に楽しめる「カチ割りワイン」を是非お試しください。